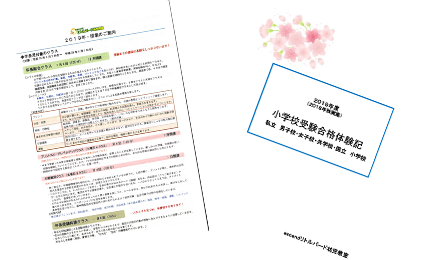暁星小学校 日曜日・木曜日コース(120分)
暁星小学校は、135年以上続く伝統を守り、キリスト教の教えを実践する人気の高い男子校です。
学校の求めている
①あきらめない子ども
②自立した子ども
③自分を大切にし他者を尊重できる子ども
④自分を律することのできる、けじめある子どもを目指します。
一次試験のペーパーや運動対策、二次試験での行動観察・協調性・発言力・機敏性を育む為の暁星小学校受験対策を強化していくコースです。
◆願書・課題作文・アンケート
・暁星小学校受験では、2021年より願書提出時に「テーマ作文」があります。ご自分の言葉を上手く伝えられるようアドバイス、添削も行ないます。
「テーマ」作文は、出願郵送時に一緒に提出します。(毎年テーマは違い、300字~400字程度、面接時に聞く場合あり)
・2024年は、一次試験に「テーマ作文」と事前「アンケート」両方あり、面接時に質問されました。
・願書は、備考欄だけ注意すれば良い位、あまり書くところが少なく負担は少ないですが、事前に「テーマ作文」や「アンケート」が加わりました。事前のテーマ作文は、提出期間が短いこともありますが、そのお手伝いや両親面接も含めご希望に従い、その添削やアドバイスは徹底的にお手伝いさせていただきます。
暁星小学校受験入試対策 <合格の秘訣>
一次試験
①ペーパー対策
暁星小学校のペーパーは全てが難しい問題ばかりではありません。
聞く力と考える力を見られます。リトルバード幼児教室では短時間での集中力を鍛え、落ち着いて指示を聞き分ける力を養い、
基本的問題をしっかり押さえ応用・発展問題に繋げていきます。
問題の量だけこなせばよいのではなく、変化球がきたときにもしっかり話を聞く力を育て最後まで諦めない集中力を育てます。
問題は、記憶・数・図形・言語・常識を中心に推理・思考の分野にも及び8枚程度にわたります。言語の分野が必ず出るのは、
入学してからの国語力の基礎、数や図形は算数の力の基礎を見るためだと思います。
毎年の出題傾向を研究し、どうしたらお子さまが理解できるのかひとり一人にあわせてアドバイスをしていきます。
毎回授業では30枚のペーパーを用意しています。(宿題30枚)ある程度広範囲をやるため、体力・気力の勝負となります。
あらゆる分野を網羅しなければなりませんが、徐々にスピードを意識し、素早く取り組む集中力を付けさせます。
②運動対策
暁星小学校の運動は、毎年大体決まったボールを中心にボールドリブル・遠投・走・行進・跳ぶなどは頻出問題として出され、
その他には行進、ケンケン、グージャンプ、その場スキップなど基礎運動と運動スキルをバランスよく見られます。
そのため毎回必ず授業の中で取り入れ苦手意識を失くし進んで取り組めるようにしていきます。
この分野でも指示を聞く力が必要です。得意になれば指示を聞くことができることから、苦手なことがないように繰り返し練習を
しなければいけません。そのためには普段から言われたことをしっかり意識して動く経験をさせていきます。
暁星小学校では特にメリハリのある機敏な動きが必要とされます。失敗しても最後まで全力で頑張ることを大切にして授業を
すすめていきます。
二次試験対策
①集団テスト(行動観察)
・近年二次試験に力を入れている暁星小学校です。一次試験で合格を頂いても二次試験もあなどれないことからペーパー、運動のみ
でなく、二次対策も同時に力を入れて行く必要があります。二次考査でも指示による制作や生活巧緻(生活の中での片付けや着脱、
ひも通し等)も多く、いかに話を聞ける子供が欲しいのかがわかります。又、最近は子供も面接がない代わりに小学校入学後にお友達
とうまくやって行けるかのコミュニケーション能力のある子どもを欲するためお友達との関わりの様子を見たり、みんなの前で発表をする
様子を見ているようです。その為、二次対策として集団での行動観察、言語発表に重きを置き毎回授業の中で繰り返し経験させて
いきます。また、常識や生活習慣ではその個々の制作・生活巧緻・指示行動も短い時間の中で行なうため、テキパキ早くどんどん作業を
進め、仕上げられるようくり返し行なっていきます。御家庭でも続けて欲しいこともアドバイスしながら教室と御家庭で一丸となり仕上げて
いきます。
集団行動での注意点
①友達と揉めない事(主張と譲歩のバランス)
②自分からの提案ができるようにする(同意もOK)
③先生の指示を聞いて自分が何をしたら良いかいけないかを判断して動く
④勝手に動かずお友達と相談しながら協力することが求められます。
面接対策
・暁星小学校受験では、2020年まで、親子で三者面談でしたが、2021年以降両親面接に変更となりました。
・2024年より、始めての「アンケート」で戸惑ったとは思いますが、テーマ作文に関しては面接でも聞かれる事もありますが、
2024年は一次試験の時書いた「アンケート」は、面接時には質問しますとはっきり書かれていますので、2日後の二次試験の面接日までに両親共にすり合わせをし、しっかり頭に入れておくようにしましょう。
また、「志望理由」「カトリック教育」「男子校」・・・等、基本的な事は早目に考えを纏めておくことが必要です。
その面接の為に志望理由や御家庭の教育方針は今まで出題されたものはまとめておくのは当然ですが、最近はネガティブな質問
(例:学校を休んで家族旅行に置くことをどう思いますか)に対し、御家庭がどの様に考えているかなどの質問が多くなりました。
それは、最近は Chat GPT の話題も増え、今までの一般的な質問に対する答えを AI が事前に答えを出し、家庭の様子が
わかりにくくなっているせいかも知れません。また、ある程度、各お教室などで面接練習をして本番に臨むため、同様の答えが多く、 本来のご両親の考える力を問う為に更に準備不可能な初めての課題を出してくることも考えられます。
そのために一緒にしっかり準備していきましょう。
・一人ひとりのお子さまに合わせたカスタムメードのカリキュラム
それぞれのお子さまのつまづきのポイントや目標・達成までの期間を考慮し、その都度個別カリキュラムを作成し、
徹底した傾向と対策で定着を図り自信につなげます。
ペーパー・生活巧緻その他内容はご相談下さい。終了後、学校選択 等、受験相談はいつでも可能です。
予約制です。日時は随時、ご相談下さい。
「何がなんでも暁星小学校に合格したい」とお考えの方はぜひご相談下さい。
★暁星小学校受験に強い、リトルバード幼児教室は全てにおいてお手伝い致します★